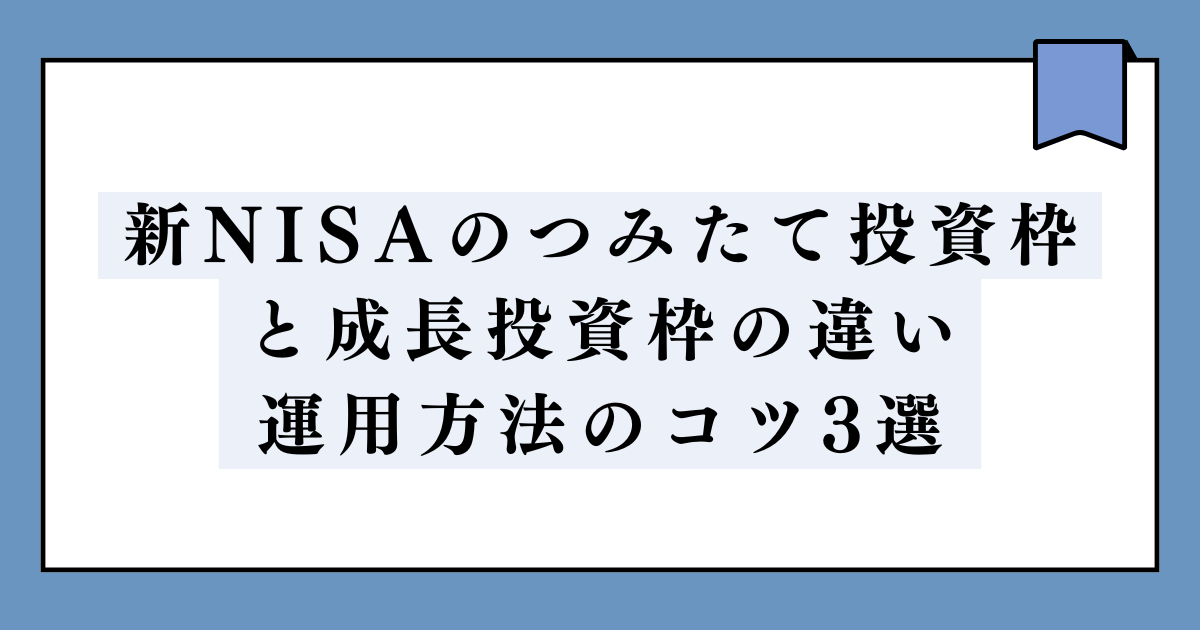この記事で解決できる悩み
「新NISAって結局いくら積み立てればいいの?」
「子どももいて支出も多い中で、老後資金って本当に準備できるの?」
そんな30代の方のリアルな悩みにお応えします。
結論から言うと、月1万円~3万円が現実的かつ老後資金を作っていくのが効果的な水準です。
本記事では新NISAを活用して着実に資産を形成中の著者が、毎月の積み立て額別に、20年後・30年後にどれだけ資産差が出るか、具体的に解説します。
実際に30代のぼくも新NISAを活用することでお金についての将来の不安を解消できていますよ!
「これなら自分にもできそう」と思える一歩を、一緒に踏み出していきましょう。
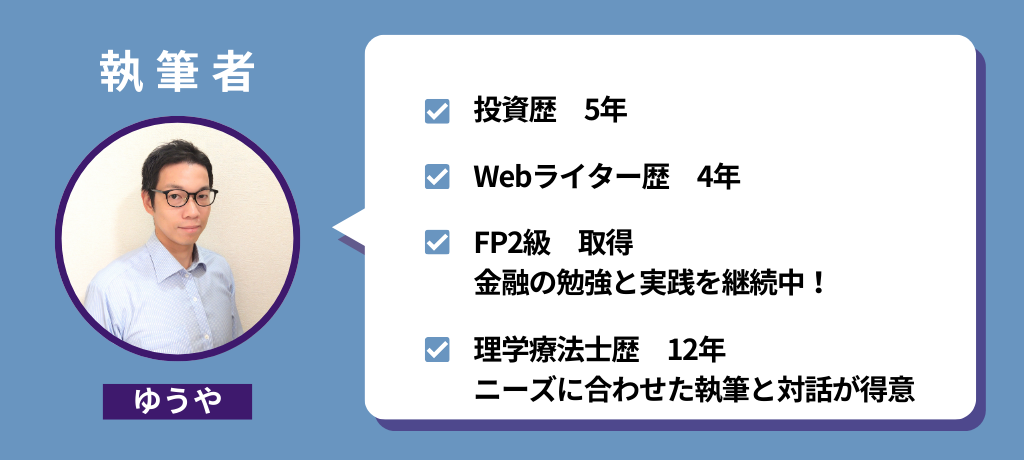
30代の適切な積み立て額
30代の新NISAにおける月々の積み立て額の目安は、月3万円~4万円程度が理想的です。
これは30代の平均手取り収入の約10〜15%に相当し、資産形成と生活のバランスを考慮した金額といえるでしょう。
ただし、この金額はあくまで目安であり、個人の状況によって調整が必要です。
家族構成や住宅ローンの有無、教育費の必要性などを考慮して、無理のない範囲で設定することが重要です。
たとえば、子どもがいる家庭では教育費を優先し、月1万円からスタートするのもいいでしょう。
もし余裕があれば、パートナーと2人で新NISA口座を開設すれば、家庭全体で月6万円~8万円の投資が可能になります。
まずは自分の生活状況に合わせた金額から始め、収入が増えたら徐々に積み立て額を増やしていく方法がおすすめです。
30代の平均積み立て額は約6万円
30代において、新NISAの月々の平均積み立て額は約6万円というデータがあります。
年代別で見ると、20代が3万円台と最も少なく、年齢が上がるにつれて積み立て額も増加する傾向です。
50〜60代では平均積み立て額は7万円前後となっています。
しかし、毎月6〜7万円という金額は、特に子育て世代の30代にとってはハードルが高く感じるかもしれません。
家計の状況に合わせて、数千円からの少額投資からのスタートでも大丈夫なので、無理のない範囲で続けることが重要です。
月々の平均積み立て額を参考にしながらも、ご自身の経済状況に合わせて投資額を設定しましょう。
収入が増えれば積み立て額を増やすなど、柔軟に調整していくといいですよ。
情報参考:金融庁 新NISA利用状況 、 オカネコマガジン(閲覧日: 2025年12月1日))
新NISAを運用した場合の利益
毎月の積み立て額によって、将来どのくらい資産が増えるか、シミュレーションで確認しましょう。
以下では、金融庁のシミュレーターを参考に、年利3%で運用した場合の資産を紹介します。
長期投資と複利の効果を確認できる内容となっていますよ。
複利とは?
もらった利息をそのまま元金に加えて再投資することで、「利息に対してもさらに利息がつく」仕組みです。
たとえば雪だるまのように、時間が経つほどどんどん大きく膨らんでいきます。
| 月々の積み立て額 | 5年後の資産 | 10年後の資産 | 20年後の資産 | 運用益合計 | 特徴・おすすめ対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 約32万円 | 約70万円 | 約164万円 | 約44万円 | 投資初心者向け。少額でも投資習慣をつけたい人に最適。 |
| 10,000円 | 約65万円 | 約140万円 | 約328万円 | 約88万円 | 家計に無理なく、将来の備えを作りたい人に。 |
| 20,000円 | 約129万円 | 約279万円 | 約657万円 | 約177万円 | 教育費や老後資金を同時に備えたい層におすすめ。 |
| 30,000円 | 約194万円 | 約418万円 | 約985万円 | 約265万円 | 本気で資産形成したい人向け。老後1,000万円の目標に届く水準。 |
月々の積み立て額で将来の資産や運用益の合計が大きく変わりますね。
それぞれの内訳についてを以下に解説します。
毎月5,000円の積み立てシミュレーション
毎月5万円を年利3%で運用した場合、5年後には約32万円の資産になる計算です。
うち運用益は2万円で、非課税のメリットは小さいですが、投資に慣れるためには良い積み立て額でしょう。
運用を10年続けると資産は70万円に増え、運用益は10万円に拡大し、20年間では、資産合計164万円となり運用益は44万円です。
20年間運用した場合、通常なら約9万円の税金がかかりますが、新NISAなら非課税です。
※税率を考慮した計算
税率 20.315%
44万円(運用益分) × 20.315%(税率) =8.9万円
少額でも長く続けることで、投資の経験を積み、資産形成につなげられます。
特に投資初心者や、無理のない範囲でまず始めたい方におすすめの金額です。
毎月10,000円の積み立てシミュレーション
年利3%で運用した場合、5年後には65万円(うち運用益5万円)、10年後には140万円(うち運用益20万円)の資産形成が可能です。
毎月1万円の積み立ても、30代会社員の多くが実践していきやすい金額だと思います。
20年後の運用結果は、元本240万円に対して運用益は88万円に達し、総資産は328万円となります。
この運用益に対する税金、約18万円が非課税になるのが新NISAの大きな利点です。
※税率を考慮した計算
税率 20.315%
88万円(運用益分) × 20.315%(税率) =17.9万円
月1万円という金額は、日々の生活費を少し見直すだけで捻出できる方も多いでしょう。
複利効果によって資産が効率的に増えていくため、30代のうちから始めれば老後資金の一部を確保する有効な手段になります。
まずは、継続しやすい金額設定で、長期投資を実践するのが重要ですね。
毎月20,000円の積み立てシミュレーション
年利3%で5年間続けると129万円(うち運用益9万円)、10年で279万円(うち運用益39万円)の資産になります。
毎月2万円の積み立ては、30代の中でも比較的余裕のある方や、本格的な資産形成を考える方に適した金額です。
20年間継続した場合、元本480万円に対して運用益は177万円となり、総資産は657万円に達します。長期的にみると、効果はさらに顕著ですね。
この際に、通常なら約35万円の税金がかかりますが、新NISAなら全額が非課税です。
毎月2万円あれば、世界中の多くの企業に少しずつ投資できる「インデックス投資」だけでなく、将来大きく成長しそうな企業や、高配当株への投資も可能となるでしょう。
卵を複数のかごに分けるような感覚で投資先を分散させて、リスクを減らせられますよ。
高配当株とは?
配当=会社がくれる「ごほうびのようなお金」
高配当株とはその「ごほうび」が多い株のこと
退職金の上乗せや子どもの教育資金など、明確な目標がある方にもおすすめです。
毎月30,000円の積み立てシミュレーション
毎月3万円の積み立ては、将来の資産形成を本気で考える30代にとって理想的な金額です。
年利3%で運用した場合、5年後には約194万円(うち運用益14万円)、10年後には約418万円(うち運用益58万円)の資産形成が可能です。
20年間継続した場合、元本720万円に対して運用益は265万円となり、総資産は985万円に達します。この際は、約53万円分が節税となります。
35歳から始めれば55歳で約1,000万円の資産が形成でき、老後への資金形成へ大きな支えになるでしょう。
お子さんのいる方は子どもの教育資金を、マイホームをお持ちの方は住宅ローンの繰り上げ返済をしながら、将来の資産形成も着実に進められます。
投資先を分散させることで、リスクを抑えつつ、より効率的な運用も可能になるでしょう。
毎月の積み立て金額に対する、将来の金額についての確認は、シミュレーションサイトを利用するのも便利です。
なお、これらはあくまでシミュレーションであり、将来を保証するものではないことはご承知ください。
参照:未来を育む資産形成 NISA(金融庁) つみたてシュミレーター 、IFAナビ 新NISAは月いくら投資すべき?
新NISAの中にある2つの投資枠を上手に活用しよう
新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つが用意されています。
2つの投資枠は併用可能で、投資スタイルや経験に合わせて使い分けをし、効率的な資産形成ができます。
つみたて投資枠と成長投資枠の特徴について知りたい方は以下の記事をお読みください。
特に30代の方は、ライフステージに合わせて新NISAの2つの枠をどう活用すべきか見ていきましょう。
まずはつみたて投資枠に投資しよう!
30代の資産形成の基本はつみたて投資枠からのスタートです。
つみたて投資枠では年間120万円まで(月10万円相当)の非課税投資ができます。
長期・積み立て・分散投資に適した金融商品が対象です。具体的には、買うときにかかるお金(販売手数料)がかからず、運用にかかる毎年の費用(信託報酬)も安いインデックスファンドなどが中心です。
つみたて投資枠の最大のメリットは、毎月自動的に投資が続けられるので、いろいろな時期に少しずつ買うことができる点です。
株価が高い時も安い時も平均的に買えるため、一度に大きく買うリスクを減らせます。
このように毎月同じ金額で定期的に買い続ける方法を『ドルコスト平均法』といいますよ。
30代は住宅ローンや子どもの教育費など支出が増える時期なので、無理なく続けられる少額からスタートし、徐々に金額を増やしていく戦略がオススメです。
成長投資枠の活用も検討しよう!
つみたて投資枠に慣れてきたら、成長投資枠の活用を検討しましょう。
成長投資枠では年間240万円まで非課税で投資でき、対象商品の幅が広いのが特徴です。個別株や、つみたて投資枠では対象外のアクティブファンドなども購入できます。
成長投資枠は特に次のようなケースで活用すると効果的でしょう。
ボーナスなど一時的にまとまった資金ができたとき。
特定の業界や企業の成長に賭けたいとき。
配当利回りの高い銘柄で定期的な収入を得たいとき。
ただし、30代の場合はリスク管理が重要です。成長投資枠では価格変動の大きな商品も選べますが、投資経験が浅い方は全体の2〜3割程度にとどめるのが無難でしょう。
基本はつみたて投資枠でインデックス投資を続けながら、余裕資金で成長投資枠を活用するようにバランスをとるのがおすすめです。
投資経験を積んだ後に徐々に成長投資枠の比率を高めていくとよいでしょう。
ぼくも投資に慣れてから成長投資枠を活用しています。
新NISAではどれくらいの額を積み立てをするべき?
これまでの内容で新NISAへ投資する適切な額について書きました。
それらの内容を踏まえて「では自分は毎月いくらくらい投資すればいいの?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。
適切な投資金額を決めるポイントを知って、効率的に資産形成をしましょう。
投資金額は収入の20~30%を目安に設定しよう
投資に回す金額は、月々の収入の20〜30%程度を目安にするとバランスが取れます。これは家計を圧迫することなく、将来の資産形成に取り組める適切な水準です。
30代は結婚、住宅購入、子育てなど大きなライフイベントが重なる時期であり、支出も増加します。
そのため、投資額を手取りの20~30%以内に抑えることで、将来の大きな支出にも備えながら無理なく資産形成ができるでしょう。
例えば、月の手取りが40万円の場合、8万円~12万円程度を投資に充てられます。
ただし、収入の20〜30%程度というのはあくまで一般的な目安です。住宅ローンや教育費など大きな固定費がある場合は、投資に回せる金額が少なくなります。
重要なのは、日々の生活に支障をきたさない範囲で投資すること。無理に投資金額を増やしすぎると、途中でお金が急に必要になったときに困ります。
特に株価が下がっているときに急いで売らなければならなくなると、損をしたまま手放すことになってしまいます。
自分の生活に余裕を持った金額での投資が大切です。
長期的な視点でつづけられる投資の金額設定が、効果的な資産形成につながりますよ。
緊急資金として3~6ヶ月分の生活費は別途確保する
投資を始める前に、まずは『もしもの時のお金』を用意しておくことが大切です。
病気やケガ、急な修理費など予想外の出費があっても困らないように、3~6ヶ月分の生活費を先に貯金しておきましょう。
万が一の疾病やケガ、予期せぬ失業などで収入が途絶えた場合でも、この貯金があれば生活を維持できます。
緊急資金と、投資のための資金は明確に区別し、リスクを取らない安全な資産で保有すべきです。
たとえば、月の生活費が30万円なら、90万円~180万円程度を貯金しておきましょう。
家族構成や仕事の安定性によってこの金額は変わります。
会社員であれば3ヶ月分、収入が不安定な自営業者であれば6ヶ月分以上を目安にするといいでしょう。
いざという時のためにお金を取っておくことで、残りのお金を長い間投資に使い続けられます。
株価が下がった時にあわてて売らずに、落ち着いて対応できる心の支えにもなるのです。
わたしは生活費の6ヶ月分を緊急資金として確保していますよ!
迷ったら月5,000円から始めてみる
「適切な投資額がわからない」という方は、まずは月5,000円という少額からスタートしてみるのがおすすめです。
新NISAのつみたて投資枠の最低投資額は多くの金融機関で100円程度からと低く設定されています。
少額から投資をスタートするメリットは、投資による心理的な負担を軽減できる点です。
株式市場が下落した場合でも、損失の額は小さくおさえられるので、冷静な判断ができるでしょう。
たとえば、月々5,000円の積み立て投資を、年率5%で20年間続けた場合のリターンを想定してみましょう。
その結果は計算上、約206万円という資産形成が期待できます。元本は120万円なので、運用によって約86万円増えることになります。
少額からでも長く継続することにより、複利効果を受けて、お持ちの資産の成長が期待できます。
新NISAを活用した資産形成は、このように小さな一歩から始めて、安心して長く続けられる投資習慣へとつながりますよ。
余裕資金があれば一括投資も効果的
月々の積み立てに加えて、ボーナスや臨時収入など、まとまった資金がある場合は一括投資も検討してみましょう。
特に市場が大きく下落した後などは、割安な価格で購入できるチャンスです。
一括投資のメリットは、早期に投資することで複利効果を最大化できる点です。
投資を始める時期は、将来のお金の増え方に大きく影響します。同じ金額を投資する場合、早めに始めた方が、最終的に形成できる資産はより大きくなります。
たとえば、100万円を一括投資して年率5%で20年間運用した場合、約265万円になります。
一方、同じ100万円を毎月約4,200円ずつ20年かけて積み立てた場合、最終的な資産額は約173万円です。
一括投資も毎月の積み立ての場合も投資総額は約100万円ですが、最終的なリターン額の差は92万円です。
一括投資のほうがリターン額が多くなっていることが分かります。
ただし、一度にまとめて投資する方法には『買うタイミングによる損得の差』が生じるリスクもあります。投資した直後に大きな値下がりがあると、実際のお金の面で大きな損失が発生します。
一括投資の良い点とそうでない点を理解したうえで、活用していきましょう。
新NISAの非課税投資枠をフル活用しよう
新NISAでは、合計1,800万円までの投資なら、生じた利益に税金がかかりません。これを生涯非課税枠といいます。
30代の方は約27年かけて新NISAの生涯非課税枠1,800万円を使い切る計算になります。
通常の投資では利益に対して20.315%の税金がかかりますが、新NISA枠内での投資なら税金がかかりません。
この税金の違いが長期的にどれだけの差になるのか、また非課税枠を超えた場合はどうなるのかを解説します。
最大1,800万円の利益に税金がかからない
新NISAには税金がかからずに投資できる金額である非課税枠があります。
新NISAでは一生涯で最大1,800万円まで非課税で運用可能です。
この非課税は長期投資において大きなメリットとなります。
例えば、1,000万円を年利5%で20年間運用した場合、通常の課税口座では約336万円の税金が発生しますが、NISA口座では税金がかかりません。
※税率を考慮した計算
税率 20.315%、 元利合計 約2,653万円、 運用益分 1,653万円
1,653万円(運用益分) × 20.315%(税率) = 約336万円
非課税メリットは複利効果とも相まって、運用期間が長いほど顕著になります。
10年間の運用では約128万円の税金差ですが、20年間では約336万円、30年間では約675万円もの差が生じます。
このように税金差が生じるのは金額が増えることで複利効果が大きくなるためです。
特に30代のような若い世代ほど、非課税によるメリットを最大限に活用できます。
例えば毎月3万円を年利5%で30年間積み立てると、課税口座では約2,550万円、NISA口座では約3,180万円と保有資産で約630万円もの差が出ます。
上記のように新NISAの非課税枠は、長期投資による資産形成を強く手助けしてくれます。
特に老後資金の準備や子どもの教育資金など、長期的な目標には非常に有効な制度といえるでしょう。
非課税枠を超過した場合は通常の課税口座で運用
新NISAの非課税枠は2つあります。
1つは1年間で投資できる金額の上限(年間の非課税枠)で、もう1つは一生のうちに投資できる金額の上限(生涯非課税枠)です。
年間の非課税枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円あります。
また、生涯の非課税枠は1,800万円です。
この枠を超える投資をしようとすると、どうなるのでしょうか。
基本的に、非課税枠を超えた投資分は、多くの場合、あらかじめ設定された一般口座や特定口座などの課税口座で購入される仕組みになっています。
多くの金融機関では、NISA口座での購入が不可能な場合、あらかじめ設定した課税口座での買い付けに切り替わる仕組みを用意しています。
注意が必要なのは、分配金の再投資も非課税枠を消費する点です。
毎月の積み立てと合わせて分配金再投資を設定している場合、年間の投資枠を知らないうちに超えてしまうことがあります。
新NISAの投資可能枠がどれくらい残っているか、時々確認するのがおすすめです。
もし年間の投資可能枠をすでに使い切っている場合でも、投資自体を止める必要はありません。
課税口座で引き続き投資を行い、翌年になったら再びNISA口座での投資を再開するという方法も有効です。
長期的な資産形成においては、非課税枠の有無にかかわらず、継続的な投資が重要です。
本記事のまとめ
30代の新NISA活用では、無理のない投資を継続することが大事です。
毎月の平均積み立て額56,102円を参考に毎月5,000〜30,000円までの積み立てシミュレーションでは、少額でも長期で着実に資産が増えることが計算できます。
理想的な積み立て額は月3〜4万円程度ですが、ライフスタイルに応じた調整が重要です。
新NISAの投資枠の活用は、つみたて投資枠からのスタートが基本で、非課税のメリットを活かした計画的な資産形成が可能です。
新NISAを通して未来への不安を解消し、楽しく充実した30代を過ごしましょう。